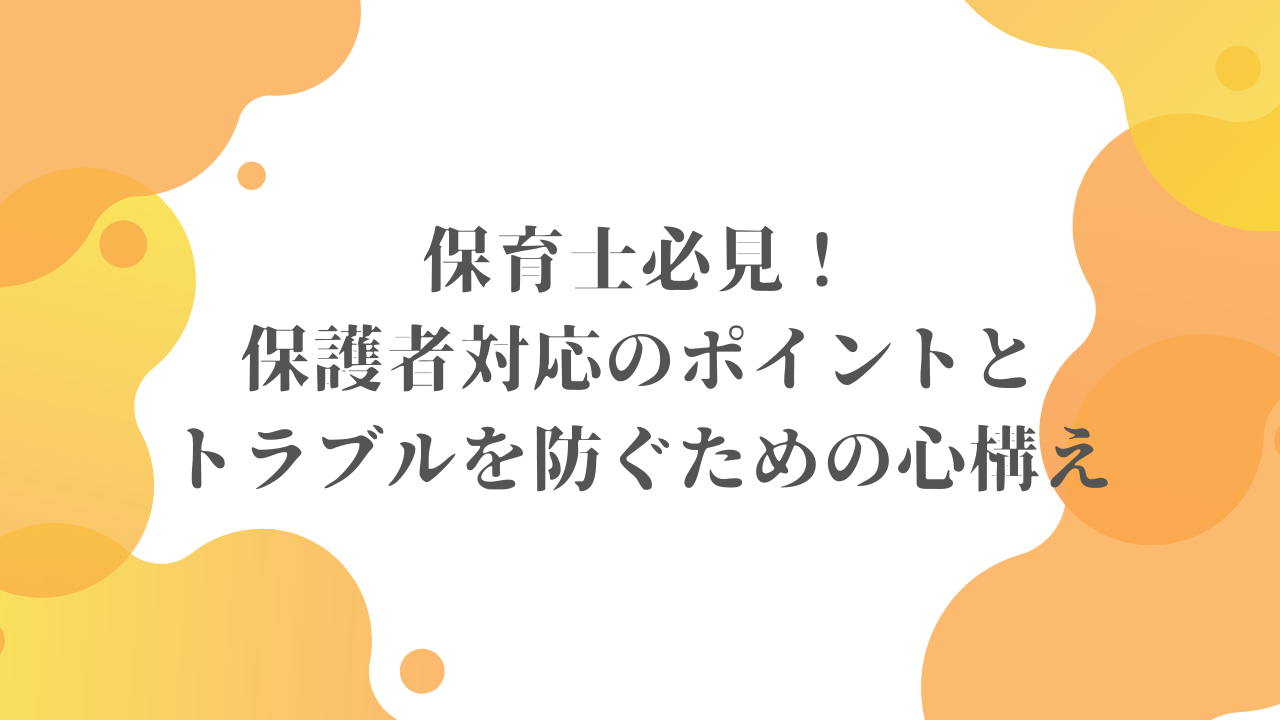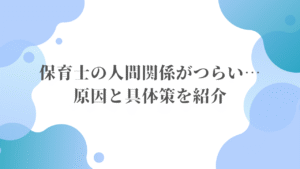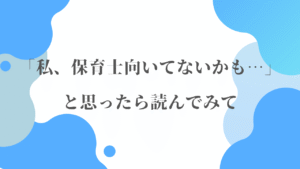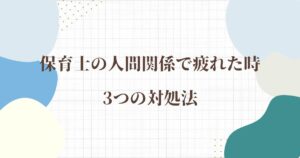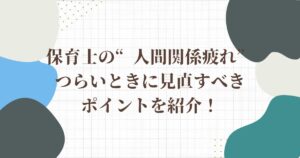※当サイトでは、読者の方に役立つ情報をお届けするため、一部の記事にアフィリエイトリンクを使用しています。リンクから商品をご購入いただいた場合、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。あらかじめご了承ください。
「3年目になって、やっと保育の仕事にも慣れてきたけど…最近は保護者対応がちょっと不安」
「マニュアルにないお願いをされたとき、どう断ればいいの?」
「断ったら関係が悪くなりそうで、怖くなっちゃう…」
そんなふうに感じたことありませんか?
保育士として経験を積む中で、保護者との関わり方に悩む機会は増えていきますよね。
今回は、よくある保護者の要望やその対応のコツ、信頼関係を崩さずに伝えるポイントをお伝えします。
よくある保護者のお願い&ご意見の具体例
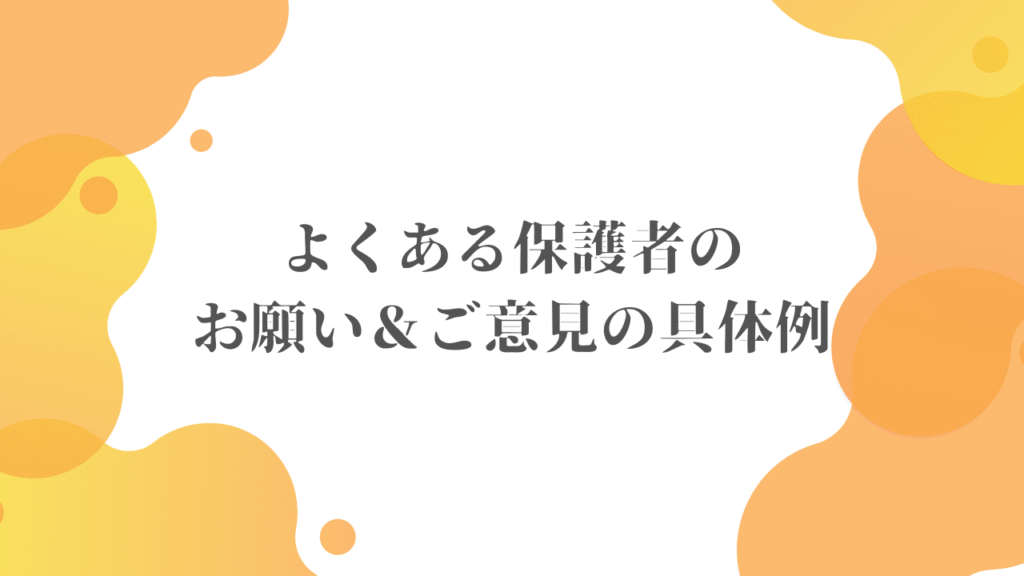
保護者の方から寄せられるご要望やご意見は、本当にさまざまですよね。
「子どもを思う気持ち」から出たものも多く、すべてが理不尽というわけではありませんが、現場では対応に迷うこともあるかと思います。
ここでは、実際によくある保護者の声をいくつかご紹介します。
もしかしたら、あなたの園でも「これ、あったかも…」と感じるものがあるかもしれませんね。
これらの例はすべてに正解があるわけではありません。
「こんなケースもあるんだな」と、少しでも参考にしていただければと思います。
個別対応の要求
保護者の方からよく聞かれるご要望のひとつに、「わが子だけの対応をお願いしたい」というものがあります。
たとえば、「お昼寝をしすぎると夜寝つけないので、昼寝をさせないでほしい」といったリクエストや、「〇〇先生にうちの子を担当してほしい」と特定の先生を希望されることもあります。
また、「給食やおやつを特別メニューにしてほしい」といった声が寄せられることも。
いずれも、お子さんを思う気持ちから出ているご要望ですが、園全体の運営や公平性とのバランスを考えると、現場では対応に悩む場面もあるのではないでしょうか。
保育時間に関するお願い
保護者からのご相談で意外と多いのが、保育時間に関するお願いです。
「開園前に預かってほしい」
「仕事の都合でお迎えが遅れるから、特別に延長してもらえないか」
このような内容は、働く保護者の状況を考えると理解できる一方で、園としての対応が難しいケースも少なくありません。
また、「今日は祖父がお迎えに行きます」など、送迎のルールに関するイレギュラーなお願いもありますよね。
急な変更や個別対応が必要になる場合、現場としては対応に頭を悩ませることもあるかと思います。
先生のプライベートに関する要求
保護者との信頼関係が深まるなかで、「先生にお願いしたい」という気持ちから、プライベートに関わるお願いを受けることもあります。
たとえば、「何かあったときにすぐ連絡したいからLINEを交換してほしい」といったご希望や、「週末に自宅で子どもを見てもらえませんか?」といった個人的な依頼も耳にすることがあります。
相手に悪気がないことも多いのですが、プライベートとの線引きが難しく、対応に悩んでしまう先生も少なくありません。
園のルールを無視した要求
園のルールや方針について、保護者からのご要望やご意見をいただくこともあります。
たとえば、「うちの子はアレルギーではないけど、給食を別メニューにしてほしい」といったお願い。
また、「おむつはずしの方法をもっと早めてほしい」「運動会の進め方を変えてほしい」といった、園の方針そのものに関するクレームが来ることも。
このような保育園のルールから逸脱したお願いに応えるのは現実的に難しいことも多いですよね。
保護者対応が難しいときの断り方|保育士としての考え方と伝え方

このように保護者対応をしていると「これはちょっと難しいな…」と思うようなお願いを受ける場面もありますよね。
でも、そういった“無理な要求”にすべて応じる必要はありません。
厚生労働省が定める「保育所保育指針(平成20年)」では、保育士の専門性を生かした保護者支援がとても重要だと明記されています。
具体的には、
- 子どもの最善の利益を第一に考えること
- 保護者の気持ちを尊重し、信頼関係を大切にすること
- 困ったときには園長や関係機関と連携すること
などが挙げられています。
子育てに悩む保護者の相談にのることも、保育士の大切な役割のひとつですが、無理な要求にすべて応じなくていいのです。
「保護者の思いを受け止めつつ、園としての対応を伝える」ことで、健全な信頼関係を築いていくことが求められています。
大切なのは、「保護者の気持ちを尊重しながら、信頼関係を築き、子どもの最善の利益を第一に考えること」。
そのためにも、園での子どもの様子を丁寧に伝えたり、日々のちょっとした成長を一緒に喜んだりできるような関係が築けると理想的です。
すべての要望に応えることはできなくても、「この先生はちゃんと子どもを見てくれている」と保護者に感じてもらえるだけでも、信頼感はぐっと高まります。
まずは「保護者も子どものことで不安があるんだろうな」と受け止める気持ちを持ちながら、園全体で協力して対応していきましょう。
保護者対応のコツ|信頼関係を保ちながら伝えるポイント
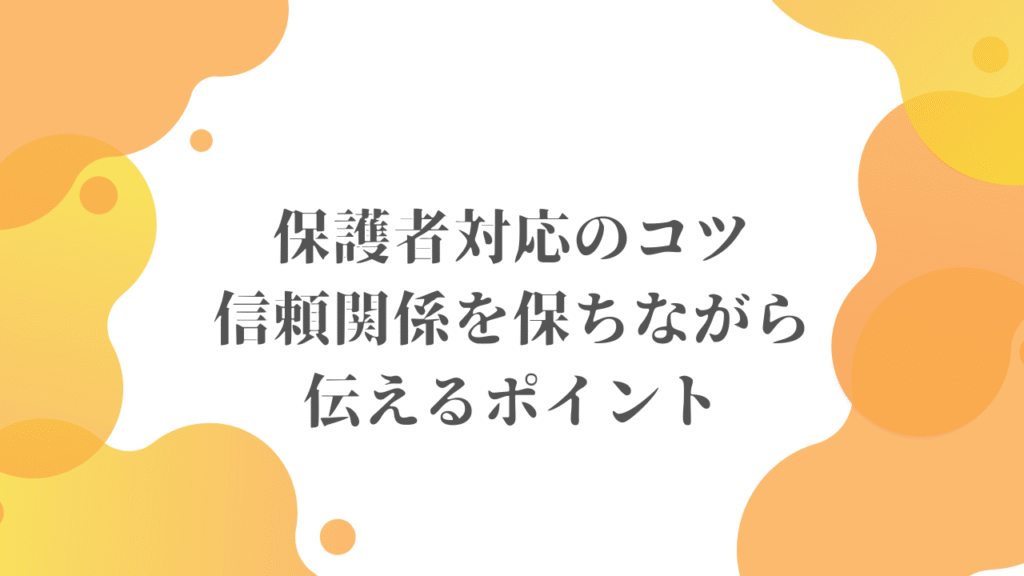
信頼関係を築いている中でも、どう返すか迷ってしまうお願いや意見もあるかと思います。
大切なのは「保護者の気持ちを受け止めつつ、園の方針を丁寧に伝えること」。
要望や意見を受けた時って、すぐ対応しなくちゃって思うかもしれませんが、
まずは焦らずに「そうだったのですね」などと保護者の気持ちを受け止めましょう。
一旦お話をすべて聞いてから、「一度クラスで確認しますね」と時間をあけるのがおすすめです。
また、一人で解決させようとせず、必ずクラスと主任や園長に状況を説明し、どのような対応していくのかを共有しておきましょう。
理不尽な要求に挟まれてつらい保育士さんへ|上司が守ってくれない時の対処法
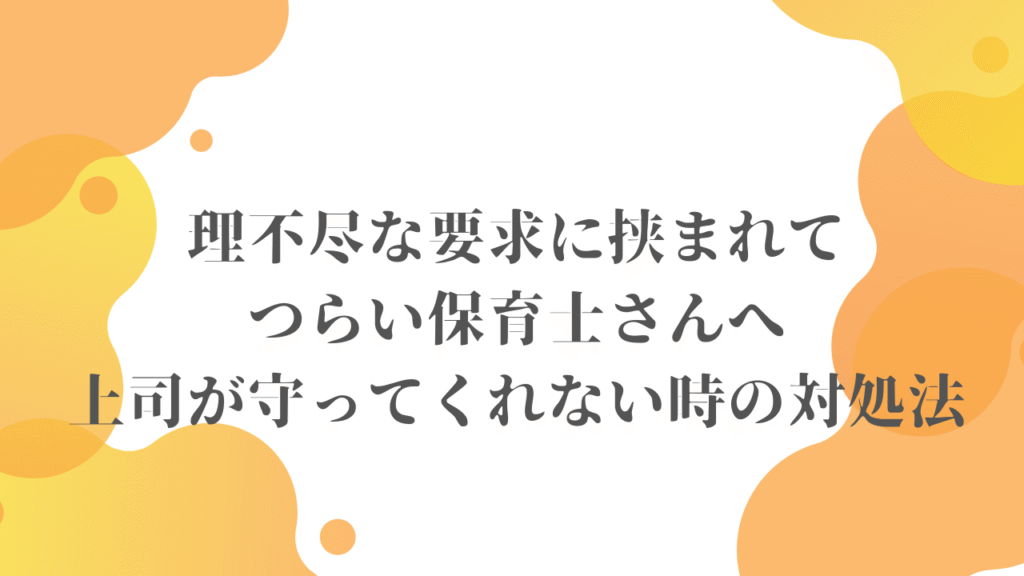
保護者からの無理な要求を丁重に断っても、引き下がってもらえなかったり、
先輩や上司に相談しても助けてもらえず、自分だけが対応を迫られたりするケースも少なくありません。
保護者と上司の間に挟まれて、自分だけが板挟みになる状況が続くと、心も体もすり減ってしまいますよね。
本来であれば、保護者対応は園全体で協力して取り組むべきもの。
上司や周囲の協力が得られないまま、理不尽な状況に一人で向き合い続けるのはとても大きなストレスになってしまい、体調を崩してしまう可能性もあります。
もしも、働き続けるのが困難だと感じたら、早い段階で転職の準備を進めてみてもいいかもしれません。
まずは無料登録できる転職サイトで、現状を相談してみませんか?
保育士専門の転職なら【レバウェル保育士】がおすすめです。
「これってうちだけなのかな?」と感じていても、実は保育園独自ルールだった、ということもあります。
一人で悩まず、エージェントに相談するのも有効です。
無料で登録できるので、よかったらやってみてくださいね。
【まとめ】保護者対応に悩んだとき、思い出してほしいこと
保護者からの要望や意見にどう対応すればいいのか悩んだら、一人で抱え込まずに、クラスや園長、主任に相談して園の方針やルールに沿って対応していきましょう。
もしも園長や主任が保護者対応のフォローをしてくれず、なかなか問題が解決しない場合は、あなたにとって無理のない環境を探すことも一つの選択肢です。
自分の心と体を大切に、無理のない働き方を目指していきましょう。