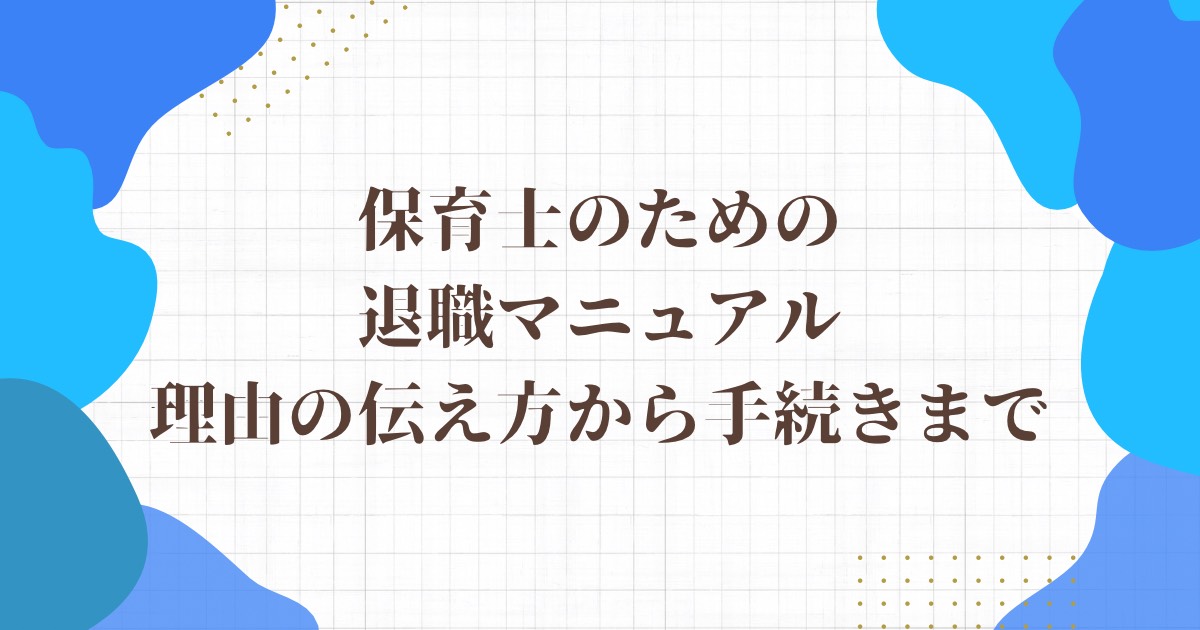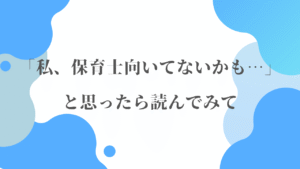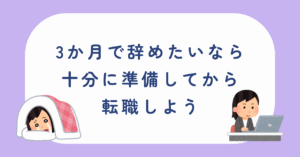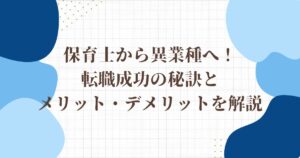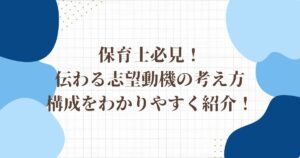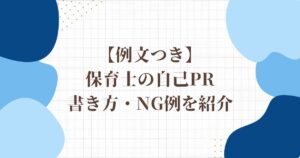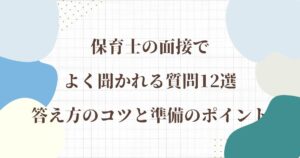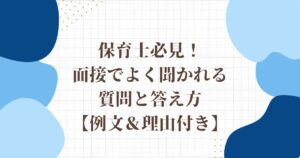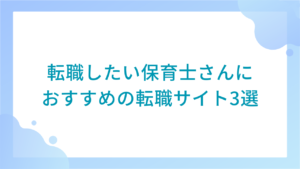※当サイトでは、読者の方に役立つ情報をお届けするため、一部の記事にアフィリエイトリンクを使用しています。リンクから商品をご購入いただいた場合、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。あらかじめご了承ください。
「退職したいけれど、どう伝えたら角が立たないんだろう…」
「退職理由を聞かれたら、何て答えればいいの?」
「園長や主任に言い出しにくくて、つい先延ばしにしてしまう…」
「他の先生にどう思われるかも気になってしまう…」
保育士として働くのは、やりがいがある一方で、職場環境や体力的な負担、
ライフスタイルの変化など、さまざまな理由で続けることが難しくなる場面はどうしてもあります。
ただ、退職の意向を伝えたいと思っても、今までお世話になった分言い出しにくいですよね。
退職の伝え方やタイミングを間違えると、退職するまで、職場との関係がギスギスしてしまって、働きづらくなってしまうこともあります。
私自身も、退職しようと思った時に園長先生やクラスの先生に「どうやって伝えよう…」と悩んだ経験があります。
なかなか言い出せなくてストレスでお腹を痛めていました…。
この記事ではそんな不安を抱える方のために、園長や主任への退職の伝え方、退職時に気をつけるポイント、そして失業保険や手続きについて詳しく解説していきます。
ぜひ、安心して次のステップへ進むための参考にしてくださいね。
保育士が退職を伝えるベストなタイミングとは?
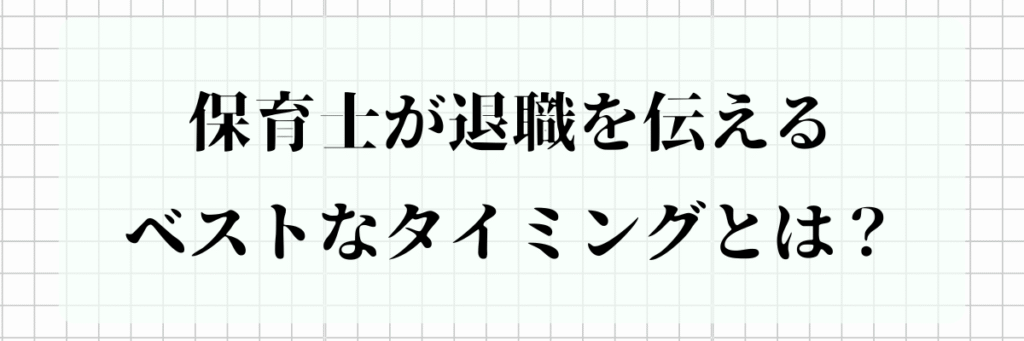
保育士の退職の意向は2〜3ヶ月前、できるだけ早めに伝えるのがベストです。
4月からの新年度に向けてクラス編成を12月頃から行うため、
退職の申し出が3月になると、新しい保育士の確保が難しくなり、園に大きな負担をかけてしまうからです。
まずは、毎年11月ごろに来年度のクラス希望を園長先生との面談で聞かれるので、そのタイミングで退職を伝えてみましょう。
もしそのような面談がない保育園の場合は、退職したい日から3か月前を目安に伝えておくのがベストです。
年度末や新年度は園も忙しいため、できるだけ早めに伝えておくとお互いに余裕を持った対応ができます。
園長・主任へ落ち着いて伝えるためのポイントと例
退職を伝えるときは、いきなり本題に入らず、段階を踏んで落ち着いて話しましょう。
まずは
「ご相談したいことがあるのですが、お時間をいただけますか?」
と面談の機会をお願いするのがスマートです。
面談の場では、
「突然のご報告で申し訳ありませんが、〇月末をもって退職させていただきたいと考えています」
と、端的に意向を伝えましょう。
緊張するかもしれませんが、落ち着いて伝えることが大切です。
退職理由にネガティブな理由をさけて簡潔に伝える
退職理由を聞かれることもありますが、無理に本音をすべて伝える必要はありません。
たとえば、「給料が安い」「人間関係がつらい」といったネガティブな内容は、あえて避けたほうがスムーズに進むこともあります。
ここでは、使いやすい退職理由の例をいくつかご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
- 家庭の事情:「家族の事情で、今後は別の働き方を考えております。」
- 体調不良や負担:「健康面を考え、仕事を続けることが難しくなりました。」
- キャリアチェンジ:「今後のキャリアを考え、新たな挑戦をすることを決めました。」
前向きな理由を伝えることで、受け入れられやすく、トラブルも起こりにくくなります。
退職するまで気をつけるポイント
退職をスムーズに進めるためには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
円満に辞めるためにも、以下のことを意識しましょう。
- 退職するまでは不満を言わないこと
退職が決まったあとでも、周囲への不満や園への批判は控えましょう。最後まで良い印象を残すことが大切です。 - 園に返すもの・提出する書類を忘れずに
保育園から貸与されているもの(名札、制服、鍵など)は、きちんと返却しましょう。退職届や保険関連の書類提出も忘れずに行います。 - 引継ぎは丁寧に行うこと
次に担当する先生が困らないように、クラスの情報や注意点など、しっかり引き継ぎをしましょう。 - 私物の持ち帰りも忘れずに
ロッカーや職員室に置いている私物は、必ず自分で責任をもって整理し、持ち帰るようにしましょう。
退職届や退職願は必要?違いや書き方を解説
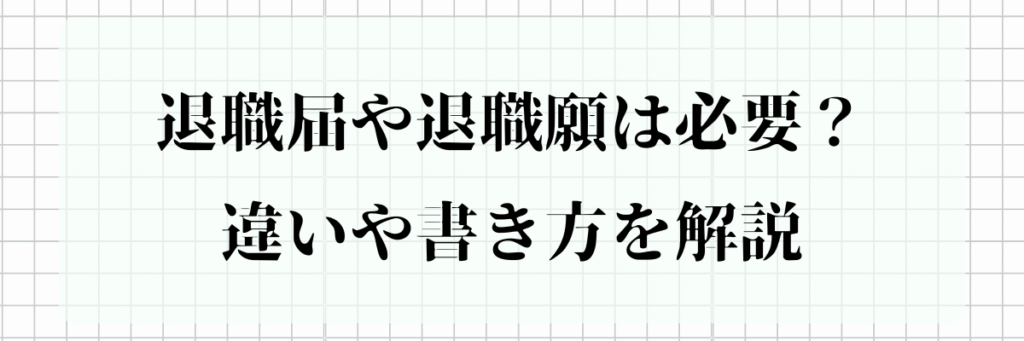
退職を伝えるとき、「退職届や退職願って必要なのかな?」と迷うこともありますよね。
面談で口頭で伝えたから、書類はいらないかも?と思う方も多いでしょう。
ただし、園によっては正式な書類の提出を求められるケースもありますので、あらかじめ違いを知っておきましょう。
- 退職願は、「退職したい」という意思を伝え、園側に承諾をお願いするための書類です。
- 退職届は、退職が正式に認められたあと、「○月○日で退職します」と最終的な意思を届け出る書類です。
つまり退職願はお願い、退職届は最終確認になります。必要に応じて提出しましょう。
退職願と退職届のフォーマット
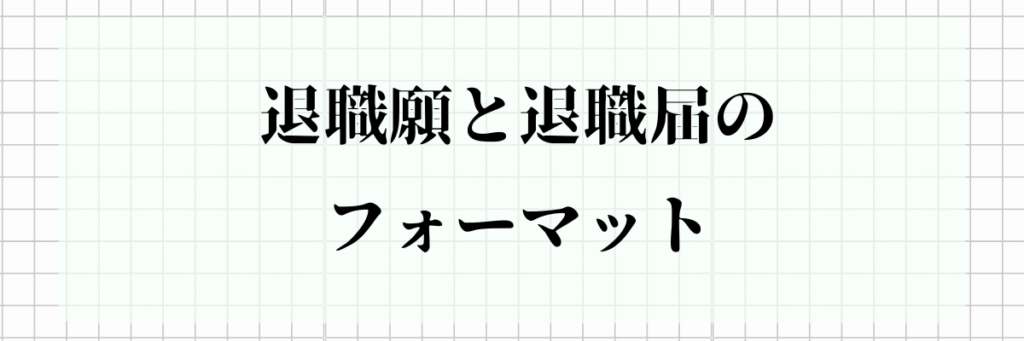
退職願と退職届、それぞれのフォーマットも紹介しますので、提出が必要になったらこちらを参考にしてくださいね。
退職願フォーマット
退職願
私事、このたび一身上の都合により
令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
(提出日)
〇〇保育園
園長 〇〇〇〇 殿
(自分の名前)
(自分の住所)
退職届フォーマット
退職届
このたび、一身上の都合により
令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
(提出日)
〇〇保育園
園長 〇〇〇〇 殿
(自分の名前)
(自分の住所)
有給休暇の消化は遠慮せずに取得しよう
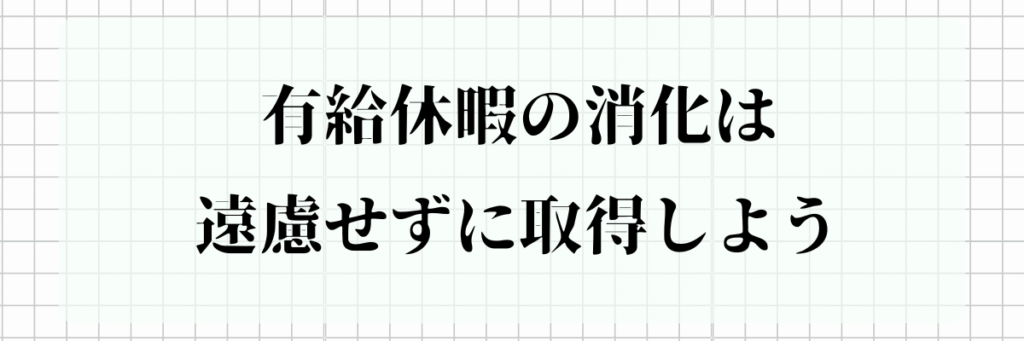
退職前には、できるだけ有給休暇を消化しましょう。
有給休暇は労働者の正当な権利なので、遠慮する必要はありません。
退職希望日から逆算して、どれくらい有給が残っているかを確認して、園長や主任に「有給を消化したい」と事前に相談しておきます。
もしも「忙しいから無理」と一方的に断られたり、取得を認めてもらえない場合でも心配はいりません。
有給休暇の取得は労働基準法で認められている権利ですので、園側に拒否権は基本的にありません。
どうしても交渉が難しい場合は、労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。
円満に退職するためにも、早めにスケジュールを調整し、無理のない形で有給を使い切れるように進めていきましょう。
有給休暇を使いたい時の相談の仕方例
相談する時の一言例
「〇月末での退職を予定しているのですが、残っている有給休暇を消化したいと考えています。スケジュールについてご相談させていただけますか?」
有給取得を断られた時の返し方例
断られたときの一言例
「有給休暇の取得は労働基準法で認められている権利だと認識しています。ご迷惑をおかけしないよう、引き継ぎなどもしっかり行いますので、取得についてご配慮いただけますでしょうか。」
保育士の退職後にやること
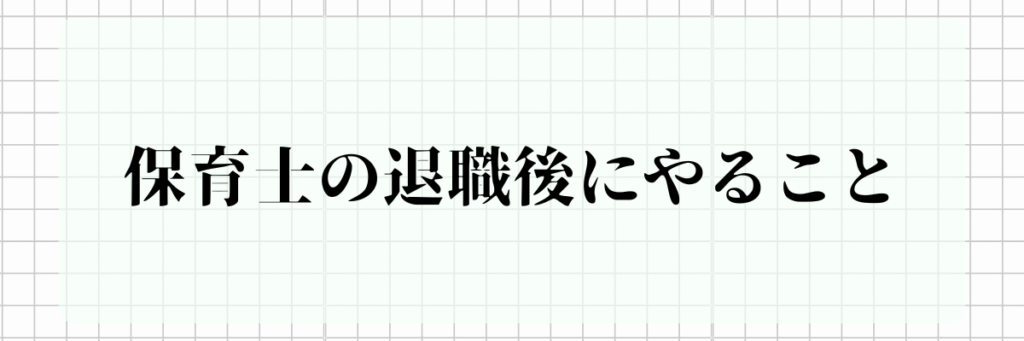
退職後は、失業保険の手続きや保育士証の登録変更など、忘れずに済ませておきたい手続きがいくつかあります。
これらを早めに終わらせておくことで、心に余裕を持って次のステップに進むことができますよ。
退職後しばらくは環境の変化で疲れやすい時期でもありますので、無理をせず、まずは自分のペースで進めていきましょう。
失業保険の受給について
失業保険(失業手当)を受け取るためには、離職の日以前の2年間で、雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。
ただし、以下に当てはまる場合は受給できないので注意しましょう。
- すぐに転職先が決まっている人
- 就職する意思がない人
- ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働くのが難しい人
失業手当は、「すぐに働きたいけれど、仕事が見つかっていない人」をサポートするための制度です。
受給を希望する場合は、退職後にハローワークで手続きが必要です。
保育士証の更新手続き
もしも退職後に引っ越しや結婚で名字が変わる場合、保育士証の登録変更手続きが必要です。
登録を行った都道府県に「登録変更申請書」を提出しましょう。
退職後、落ち着いてから転職活動をはじめよう
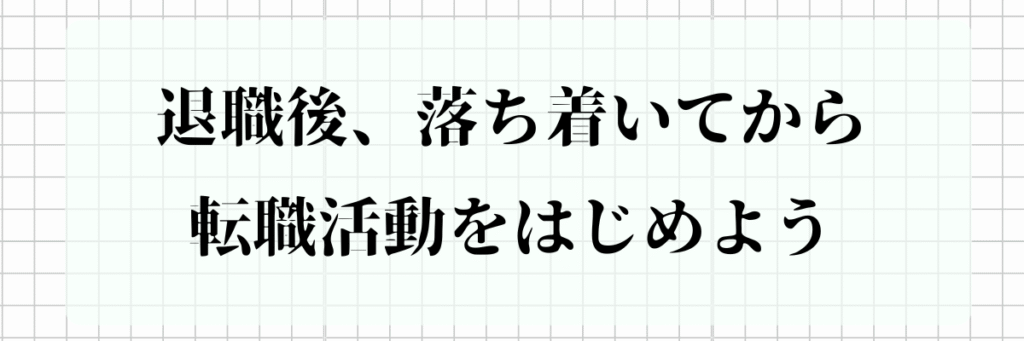
退職後は、こんなふうに考えている方も多いのではないでしょうか。
- 「少し休んでから転職先を探したい」
- 「引っ越しが落ち着いてから考えたい」
- 「焦らず、自分に合った職場を見つけたい」
そんな方は、落ち着いてから転職サイトに登録して情報収集を始めるのがおすすめです。
もちろん、退職直後にすぐ動き出してもいいのですが、
心と体が疲れているときに慌てて動くと、 「連絡が多すぎてうんざり…」と負担になってしまうこともあります。
「よし、今ならがんばれそう!」と思えたタイミングで動くほうが、転職活動もうまくいきやすいですよ。
保育士専門の転職なら【レバウェル保育士】がおすすめです。
無料で登録できるので、気軽に情報を集めるところから始めてみてくださいね。
まとめ|無理せず、自分を大切に退職を進めよう
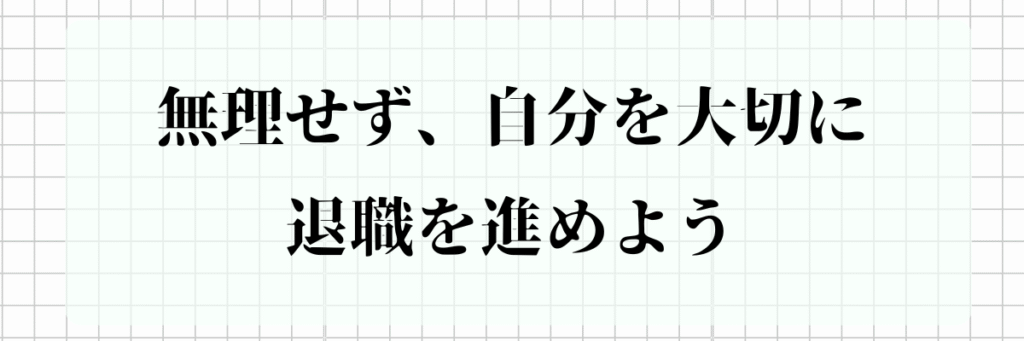
退職は、決して悪いことではありません。
これまで頑張ってきた自分を認め、次のステップに進むための大切な一歩です。
お世話になった先生方へ退職のことを伝える時は、焦らず、丁寧に伝えるよう心がけましょう。
新しい未来に向かって、一歩ずつ進んでいけるよう応援しております。