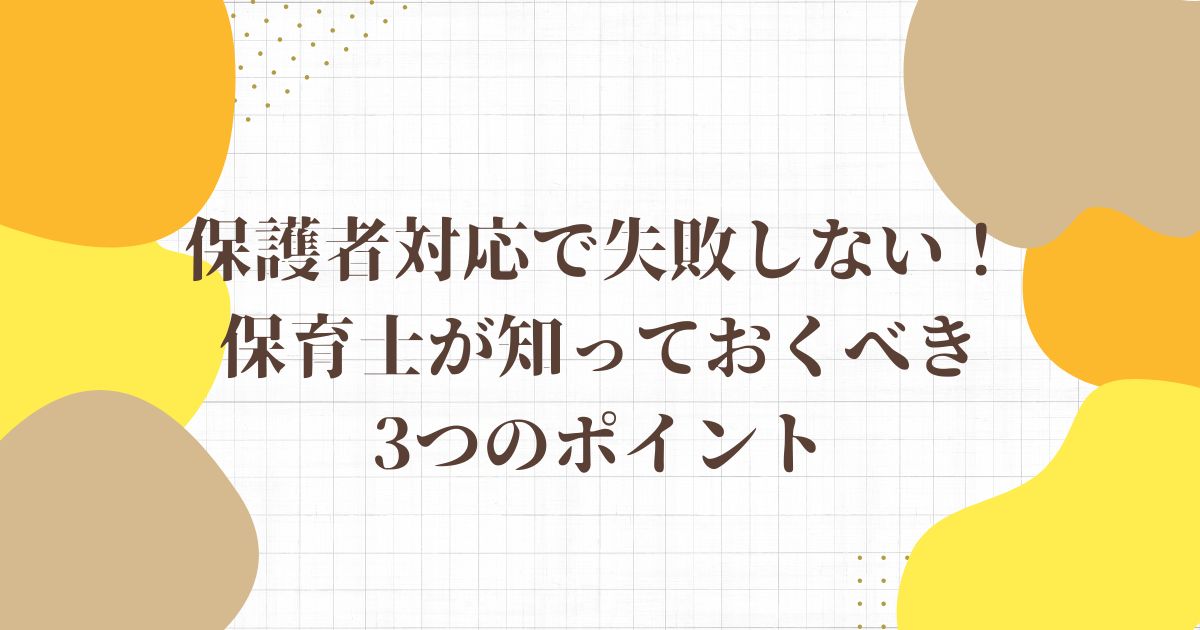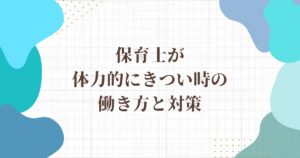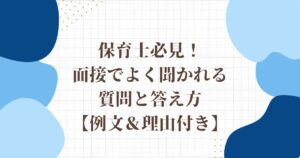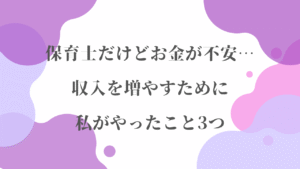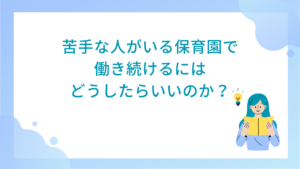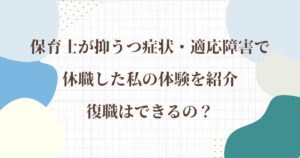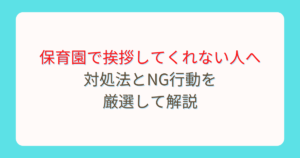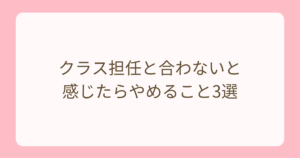※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

対応がうまくいかなくて、保護者に怒られちゃったな…。
それに比べて、先輩保育士さんは保護者の方と仲良くお話しされててすごいなぁ。
どうしたらあんなふうに話ができるんだろう。
保護者対応での失敗は、どんなに気を付けていても、一度は経験してしまうものです。
けど、できるなら保護者対応で失敗したくないし、良好な関係を築きたいと思うはず。
そこでこの記事では、よくある失敗例とその対処法、対応のコツをお伝えします。
あらかじめ「こんな失敗があるんだな」と知っておけば、普段から気を付けられるかもしれません。
よかったら参考にしてみてくださいね。
保護者対応でよくある失敗パターンの紹介
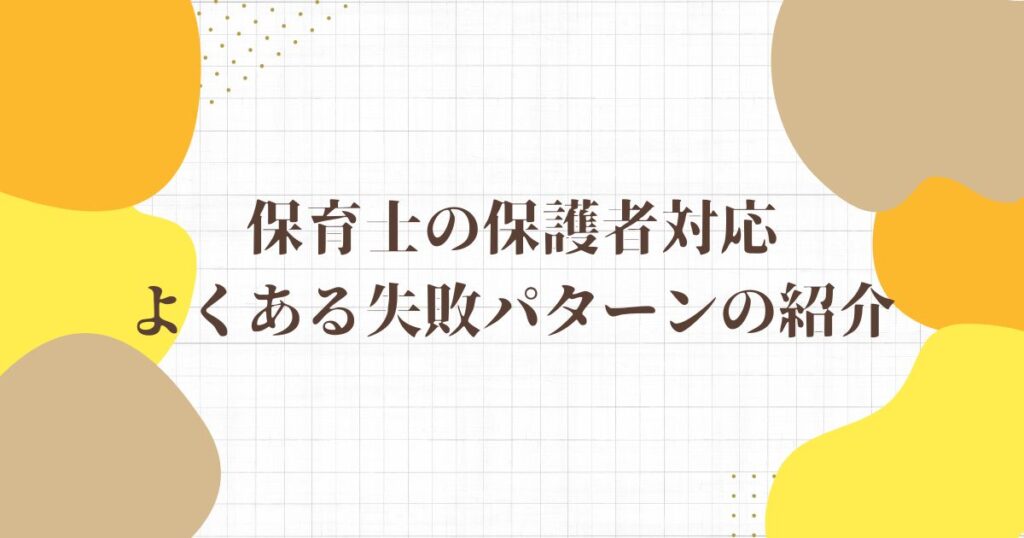
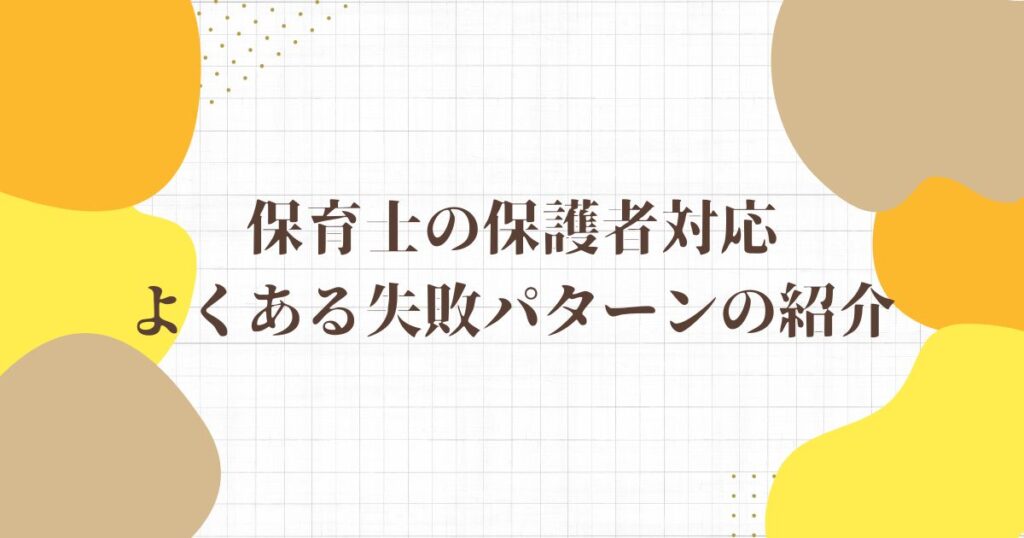
保育士のミスが原因で保護者対応がうまくいかなかった例をご紹介します。
どれも、意識していれば防げることかもしれませんが、毎日の忙しさの中でつい後回しにしてしまったり、うっかり忘れてしまったりすることってありますよね。
でも、そうした小さなミスの積み重ねが、保護者との信頼関係に影響を与えてしまうこともあります。
「これ、私も気をつけよう」と思いながら、ぜひ参考にしてみてくださいね。
保育士間の共有のし忘れ



朝、お母さんから
「すみません、ズボンを持ってくるの忘れてしまいました。
今日は、午前中にお迎えに行くので、今履いてるズボンのままで大丈夫です」と言われたんです。
そのとき私は「わかりました」って返事をしたんですが、クラスでちゃんと共有していなくて…。
後から別の先生が「ズボンの替え、どうしたんですか?」って聞いてしまって、お母さんから「朝、伝えましたけど…」って怒られてしまいました
口頭でのやりとりって、つい他の先生に伝えそびれてしまう時があるんですよね。
特に朝はバタバタしているので、なおさら忘れやすいです。
でも、それが何度か続いてしまうと「この園はちゃんと共有してくれないんだ…」と保護者の方に不信感を持たれてしまうことも。
だからこそ、口頭で言われたことはすぐにメモをとるか、近くにいる先生に「さっき〇〇さんがこう言ってました」と一言伝えておくことが大切です。
表情で誤解を与えてしまった



朝早くから出勤してたせいか、もう夕方の16時には眠くて眠くて…。
自分では普段通りに保護者対応していたつもりだったんですけど、
お母さんから
「うちの子、なにかありましたか?」って聞かれちゃって…。
もしかしたら、私の顔が疲れてどんよりしてたのかも…と、
あとでハッとしました。
ちょっとした表情や声のトーンひとつで、保護者の方を不安にさせてしまうケースは、実は少なくありません。
特に疲れていたり考えごとをしていたりする時は、
自分では普通に接しているつもりでも相手には冷たく感じられてしまう場合もあります。
意識して笑顔を心がけたり、声をワントーン明るくするよう心がけてみましょう。
質問の回答が伝わりづらい言い方をしていた



ある日、お母さんに
「うちの子、抱っこだと寝なくて…
保育園の睡眠時間が短いようですが、どうやって寝かせてるんですか?」
って聞かれました。
つい何気なく「保育園では、あまり抱っこして(眠って)いませんね」って答えたんです。
そしたらお母さん、
ちょっと表情を曇らせて、「うちの子、抱っこしてもらえてないんですか…?」って。
そんなつもりじゃなかったんですけど、
伝え方で誤解させてしまったのかもしれません…。
保護者の言葉をそのまま受け取るのではなく、その背景にある気持ちを想像することが大切です。
たとえば、先ほどの例のお母さんの場合、
「保育園での睡眠時間が短いけど大丈夫かな?」
「ちゃんと休めているのかな?」
このような不安が、会話の中から読み取れますよね。
保護者の気持ちにもそっと寄り添うようにすると、安心感を持ってもらいやすくなりますし、 そうした思いやりのある対応が、信頼関係を深める第一歩にもつながります。
反射的に『聞いてないです』と言ってしまった
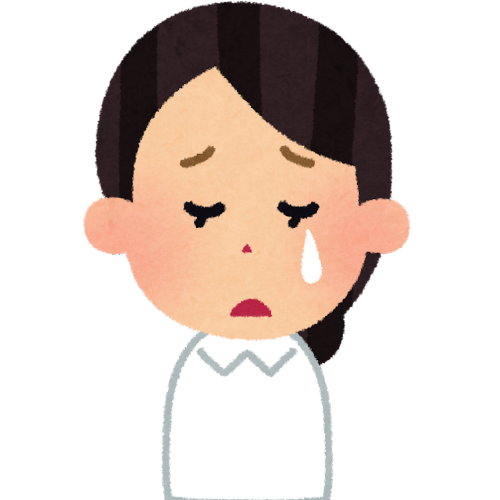
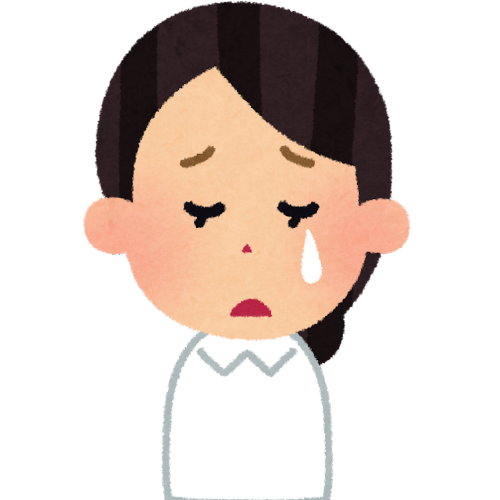
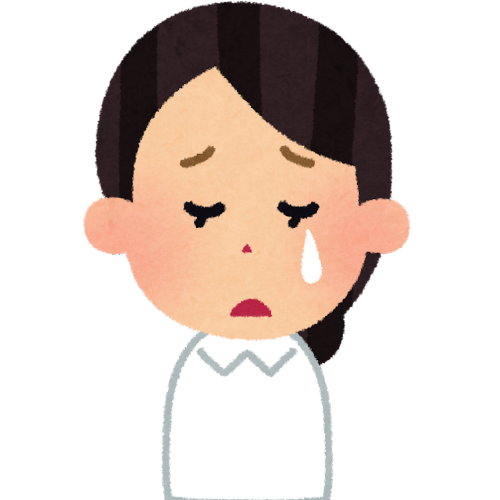
お迎えの時、保護者の方がちょっと困ったような顔で話しかけてきました。
「朝、着替えを袋に入れて渡したんですけど…使ってもらえなかったんでしょうか?」
私は、ついその場で反射的に「え?聞いてないです。」と答えてしまいました。
その瞬間、保護者の方の表情がスッと変わって、
「え…ちゃんと朝、お渡ししましたけど?」と少し強い口調に。
後から確認したらほかの先生が対応されていたそうで、私には共有されていなかったんです。
それ以来、そういった場面では即答せずに「すみません、こちらで確認できていなかったかもしれません。少し確認してきますね」と伝えるようにしています。
こういうやり取りって、忙しいとつい反射的に返してしまうことがありますよね。
しかし「聞いてない」って言葉は、保護者の方にとっては「ちゃんと伝えたのに…」と不信感を感じさせてしまうかもしれません。
たとえあなたが事実として聞いていなかったとしても、まずは状況を落ち着いて確認しましょう。
「こちらの確認不足かもしれません、少し確認してきますね」と一呼吸おいた伝え方を意識するだけで、印象は大きく変わりますよ。
保育士の保護者対応 失敗しないための3つの基本的な考え方
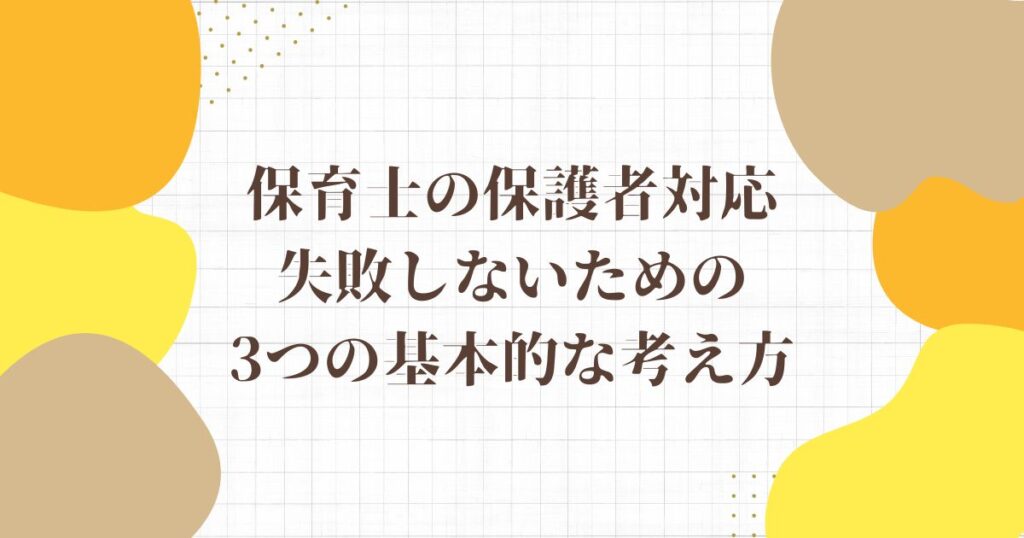
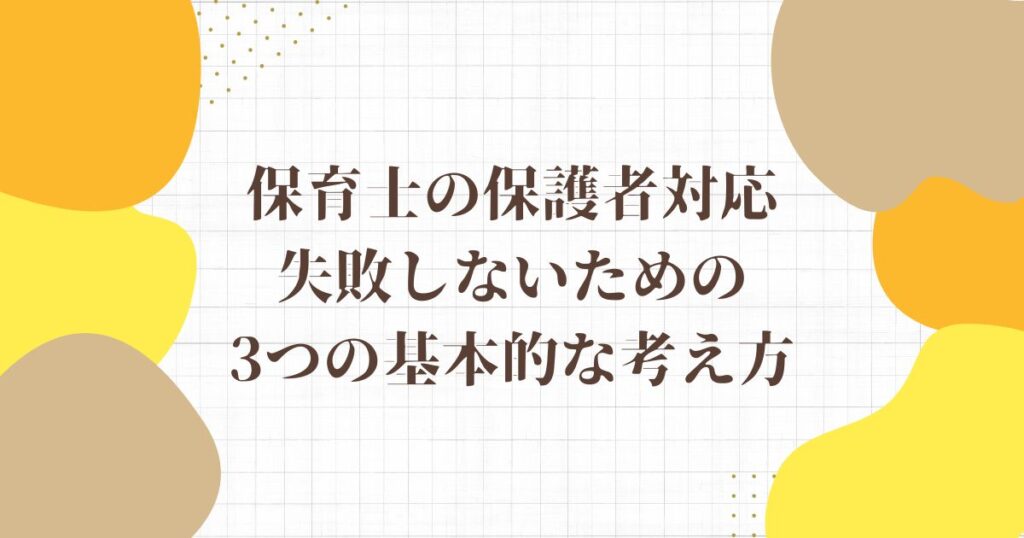
保護者対応って、正直むずかしいな…と思うこと、ありますよね。
伝えたつもりが伝わっていなかったり、ちょっとした一言で誤解を招いてしまったり。
「こんな言い方でよかったのかな?」と、あとから不安になることも少なくありません。
ちなみに、保育所保育指針の保護者支援ではこう書いてあります。
1.保育所における保護者に対する支援の基本
(1) 子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。
(2) 保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。
(3) 保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保
育所の特性を生かすこと。
(4) 一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育
力の向上に資するよう、適切に支援すること。
(5) 子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基
本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。
(6) 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄
の秘密保持に留意すること。
(7) 地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係
機関、団体等との連携及び協力を図ること。
これらを土台として、
保育士には「伝え方」や「接し方」など日々の関わり方においても丁寧な姿勢が求められています。
それもふまえつつ、保護者対応で失敗しないために気を付けることや
失敗した後に大切な3つの基本的な考え方についてご紹介します。
どんなに準備していても失敗する時はある
失敗してしまった瞬間は、本当に落ち込みますよね。
だけどどんなに経験を積んでいても、どれだけ準備をしていても、失敗してしまうことはあります。
失敗するのが怖いからといって保護者対応をしないというわけにはいきません。
失敗は誰にでも起こりうることで、
「私も、あなたも、いつかは失敗するもの」と思いつつ、保護者対応に向き合っていきましょう。
そして、失敗して謝罪をきちんとした後には、逃げずに関わりを持ち続けることも大切です。
きちんと謝罪した後は、今の自分にできることを考えて、これまでと同じように丁寧に関わっていけば大丈夫ですよ。
子どものために、言わなきゃいけないことはきちんと伝える
それでも失敗したあとの保護者対応って、正直すごく気まずいですよね。
「できれば関わりたくないな…」と思ってしまうのも、自然な気持ちだと思います。
子どもの成長や安心のために保育士として伝えなければいけないことは、これからもきちんと伝えていく必要があります。
一方的にならないように、「保育園ではお子さんの成長のために、こういう考えで保育しています」と、丁寧に伝えていきましょう。
失敗の後こそ、信頼を築き直すチャンス
保護者対応で失敗した後こそ、信頼関係を築き直すチャンスです。
失敗して一時的に信頼を失ってしまったかもしれませんし、迷惑をかけてしまったかもしれません。
ですがくじけず、日々の丁寧な関わりを積み重ねていきながら、信頼関係を築き直していきましょう。
子どもに対して優しく声をかけたり、一緒に笑ったりするような普段の姿は保護者の方にもしっかり届いているものです。
過剰に気を使いすぎなくても大丈夫です。
保護者の方は「子どもに誠実に向き合ってくれているかどうか」をしっかり見ています。
逃げずに向き合おうとする姿勢が、信頼を取り戻す大切な一歩になります。
もし失敗してしまったら?その場ですぐできる対処方法を紹介
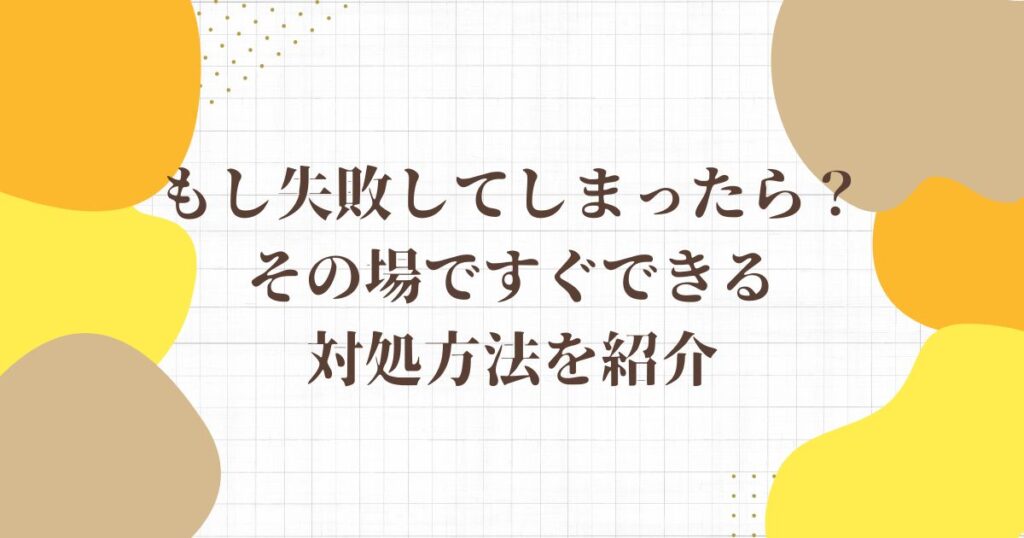
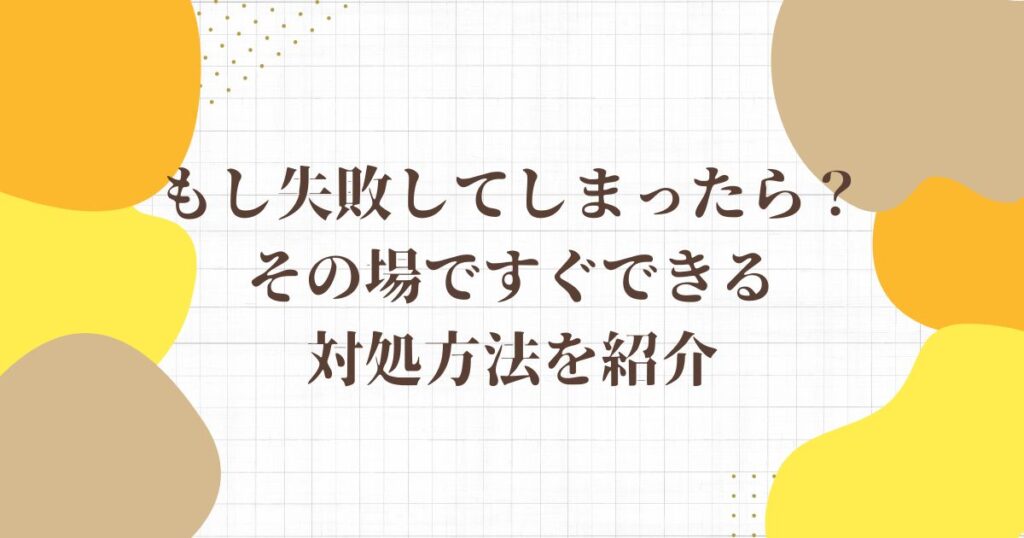
どんなに気をつけていても、保護者対応で失敗してしまうことはあります。
ここでは、実際に失敗した!という時に使える対処方法を紹介します。
まず一番大切なのは、保護者の話をしっかり聞いて受け止めること。
「話を聞いてくれた」と感じてもらえるだけで、安心につながります。
次に、誠実な姿勢で謝ること。
しっかり「大変申し訳ございません」と伝えて、気持ちが伝わるように意識しましょう。
そして、対応を一人で抱え込まないこと。
主任や園長に早めに報告・相談し、園全体でのサポート体制を整えることが信頼回復の近道になります。
ぜひ意識してやってみてくださいね。
実際に失敗した保育士のリアルな声(体験談)
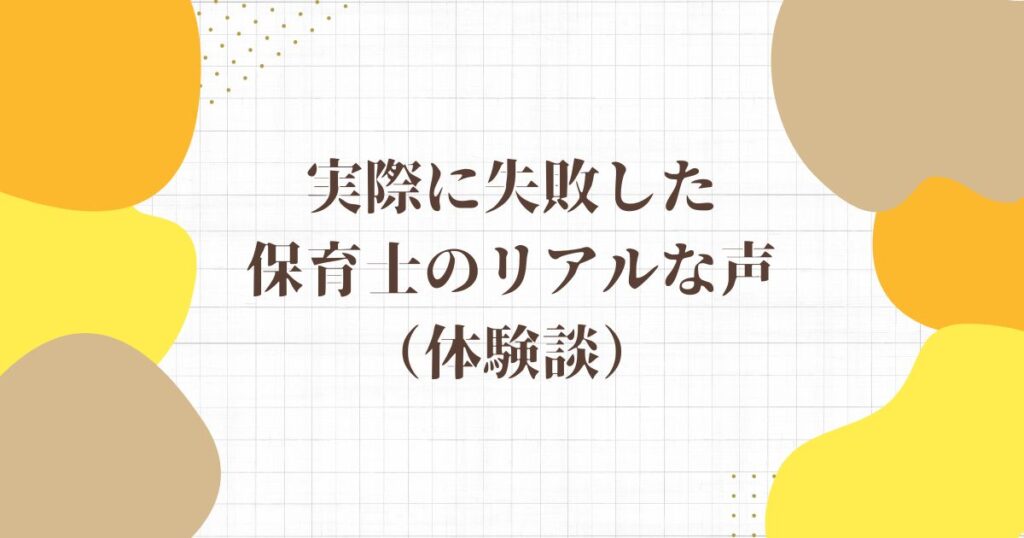
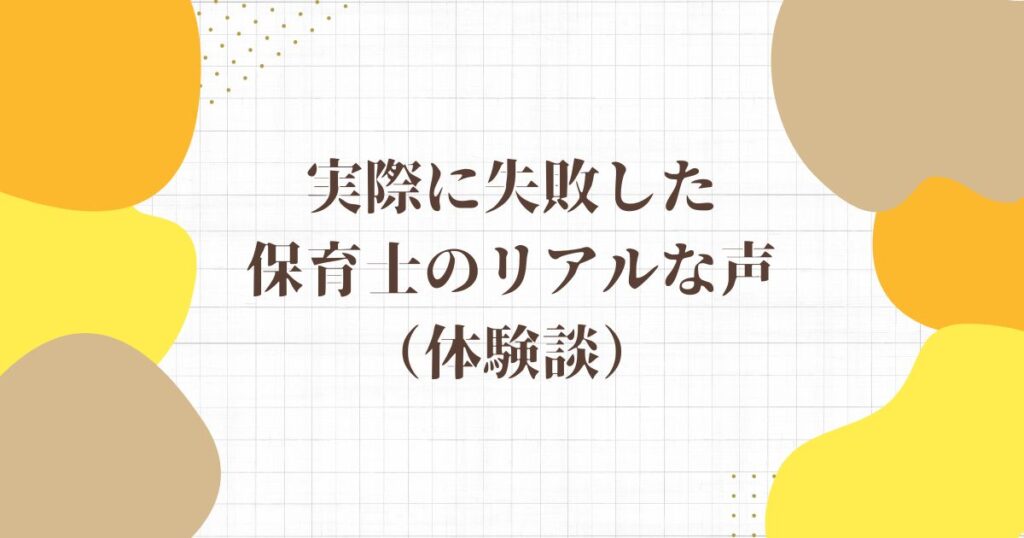
保護者対応での失敗は、経験を積んだ保育士でも、伝え方やちょっとした気配りでつまずくことがあります。
ここでは、実際に失敗した方のリアルな体験談についてご紹介します。
「私だけじゃなかったんだ」と少しでも安心できたり
「こうすればよかったのか」と気づきを得たりするきっかけになれば嬉しいです。
言い方ひとつで不信感を与えてしまった
お迎え時に、保護者から「今日は給食ちゃんと食べられましたか?」と聞かれて、「今日はあまり食べなかったですね。最近ちょっとムラがあります」と答えました。
すると保護者が不安そうな顔に曇ってしまい…。
その時は何も言われませんでしたが、後日「もっとフォローの言葉がほしかった」と園長に相談が入り、事実確認が入りました。(女性/保育士 3年目)
事実を伝えたつもりでも、「言い方が冷たかった」「否定された感じがした」と捉えられてしまう可能性があります。
「でも〜していましたよ」「こんな姿もありました」と、補足やプラスの言葉を添えるようにしてみましょう。
連絡帳に書いたつもりが文章がわかりづらくて伝わっていなかった
午睡中にお腹が冷えていたので、シャツを着替えた旨を連絡帳に記入したところ、文章が曖昧で、「お腹の調子が悪かったのか?」と保護者が不安になってしまったそうです。
翌朝「昨日の連絡帳、ちょっと気になって…」と指摘されて初めて気づいたようですが、書いた本人にしかわからない内容だったと反省したそうです。(女性/保育士1年目)
自分の中では伝えたつもりでも、読み手にとっては「どういう意味だろう?」と受け取られてしまうことも。
特に連絡帳は、保護者にとって子どもの一日の様子を知る大切な手がかりです。
「なぜそうしたのか」「子どもはどうだったのか」を、
できるだけ具体的に、短くても伝える工夫があると安心感につながります。
状況+補足の一言があると誤解を防ぎやすいでしょう。
うちの子だけ注意されている”と保護者に言われてしまった
クラスのお友達とうまく関われないお子さんがいたので、その子に寄り添いながら、うまく関われるように声かけをしていました。
ところが、夕方その様子を見ていた保護者の方から「うちの子だけ目立って注意されているみたいで、ちょっと気になります」と声をかけられました。
もちろん保育の意図があって関わっていたのですが、他の子と同じように声をかけていても、“特定の子だけ厳しくされているように見える”ことがあるんだなと、ハッとさせられました。
それからは、お迎えの際に「今日はこんな姿がありました」「こういう関わりをしています」と、意図を伝えるひと言を添えるように意識しています。
こちらは丁寧に関わっているつもりでも、保護者が見るタイミングや伝え方ひとつで、保護者に違った印象を与えてしまうことがあります。
だからこそ、日々の関わりの「意図」を保護者に伝えることって、本当に大切だなと感じます。
「今日はこんなことができましたよ」
「こんなふうに関わっています」
といった前向きな言葉を添えるだけでも、安心感や信頼につながりやすくなります。
まとめ:失敗を恐れすぎず、改善を重ねよう
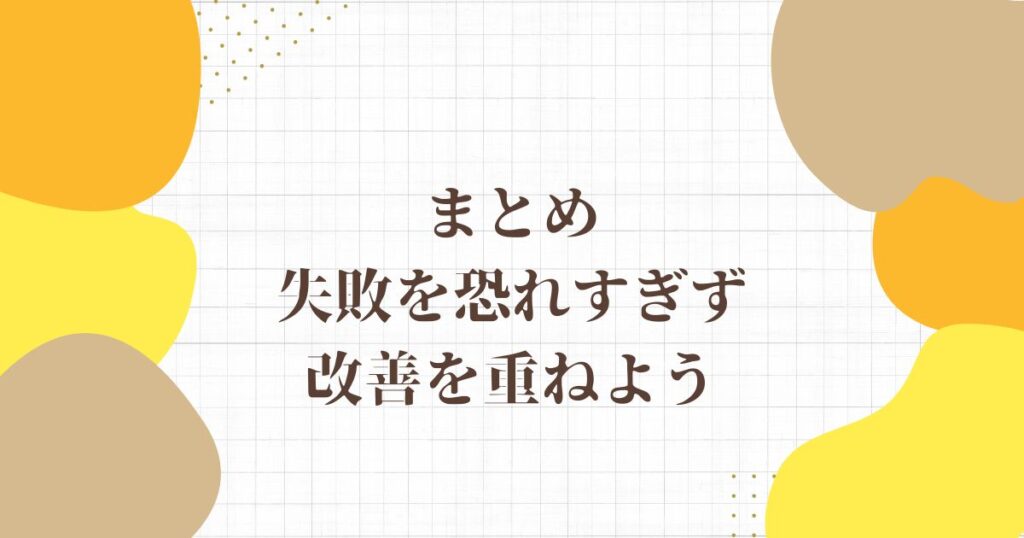
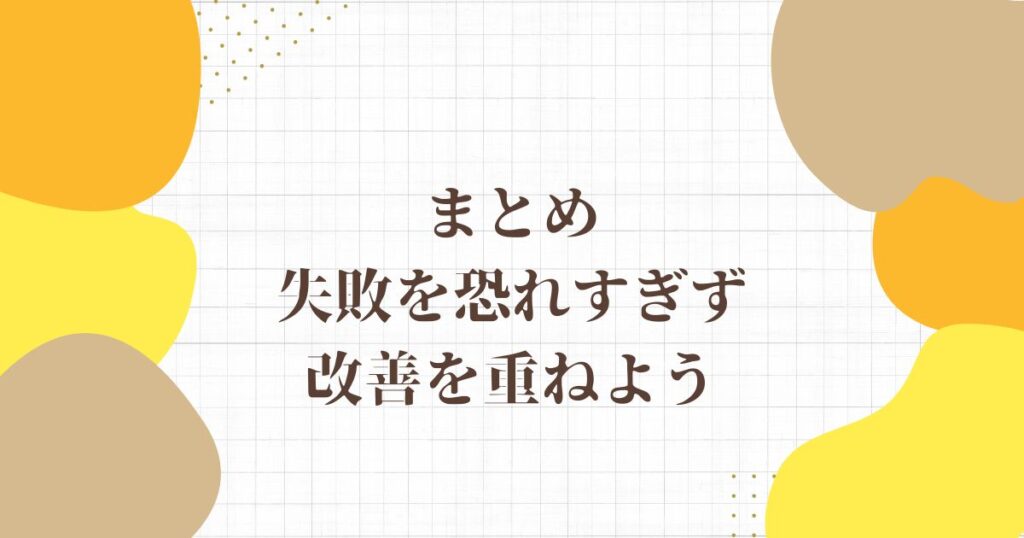
保護者対応は、正解がひとつではないからこそ、悩んだり失敗したりするのは当たり前です。
大切なのは、「失敗しないこと」ではなく、「どう立ち直って、どう関わり続けるか」。
今回ご紹介したような失敗例や考え方を日々の中で少しずつ意識していくことで、
あなた自身の“伝え方の引き出し”が増えていくはずです。
完璧じゃなくても大丈夫ですので、少しずつ信頼関係を築いていきましょう。
「今の職場でいいのかな…」と感じているなら環境を見直してみよう
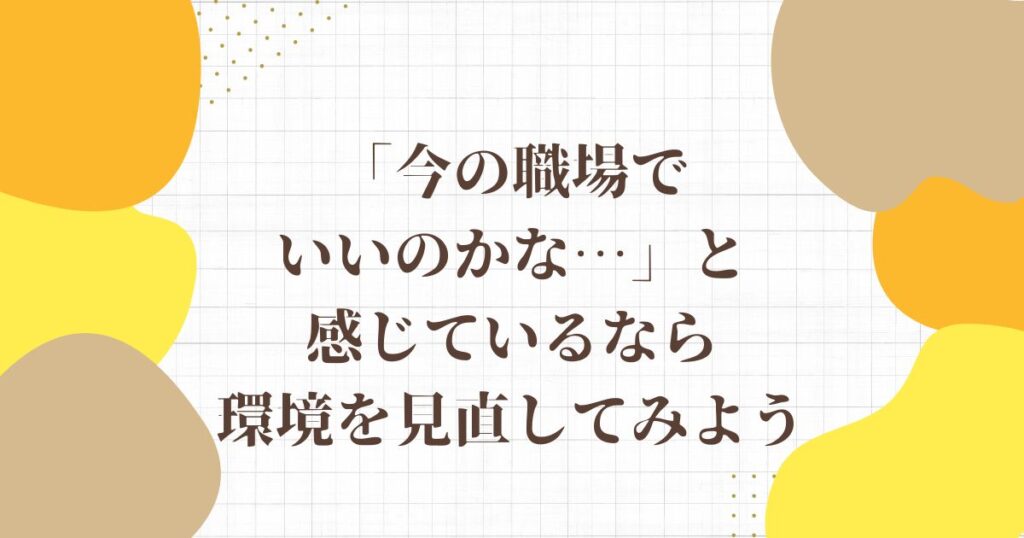
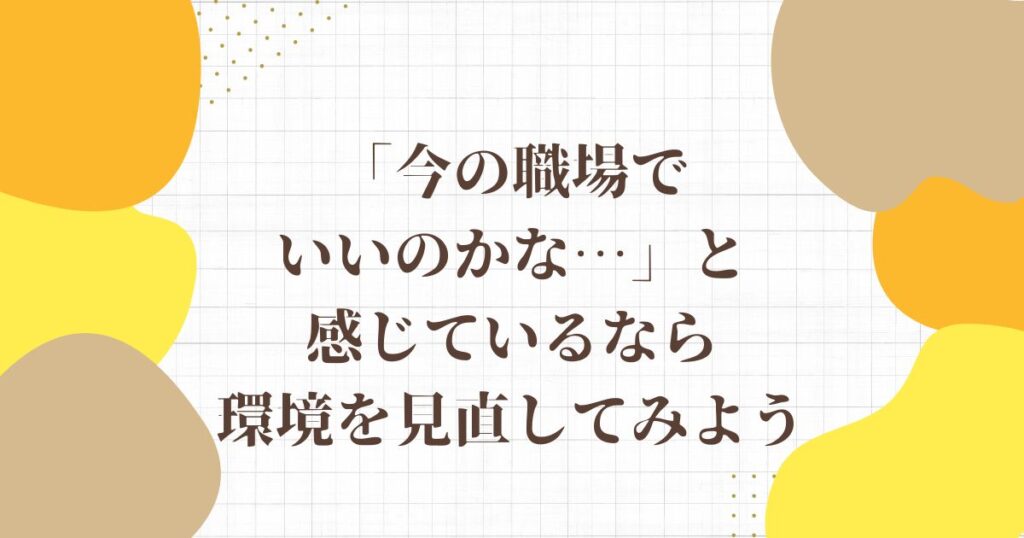
もし今の職場での対応に不安を感じているのなら、環境そのものを見直すことも選択肢のひとつです。
園の方針や人間関係、サポート体制によって、保育士の働きやすさは大きく変わりますから、
無理をしすぎる前に、まずは情報収集から始めてみませんか?
保育エイドなら、1分で登録できます。
今の職場ってどうなんだろう…と悩んだ時はぜひ登録してみてくださいね。